本文
里山の恵み生かした草木染め “黒”が映える絹ストール
目指せ!石川発の人気商品
ヒットの予感
石川県が創設した「いしかわ産業化資源活用推進ファンド(活性化ファンド)」の認定企業にスポットを当て、地域の資源を生かした商品開発について紹介する。
普段使いから喪の席まで使い方はいろいろ
穴水町で着物などの染色加工に取り組む新谷工芸では、草木染めの絹ストール「黒の装い」の制作・販売に力を注いでいる。「黒の装い」は、丹後ちりめんを地元の落葉樹ヤシャブシの実で黒とグレーの2色に染め上げ、グレー部分に墨絵でツタなどの繊細な模様を描いて仕上げる。
 30年以上にわたってあつらえの着物を手がける新谷茂代表が絵柄を手描きし、熟練のスタッフが手絞りを担う。どの工程も機械に頼ることは一切ない。「化学染料ならば30分ほどで終わるところが、草木染めでは白からグレーにするだけで3時間かかる」と新谷代表。完成までに20もの工程が必要で手間はかかるものの、そこには手仕事ならではの気品や風合いが漂っている。
30年以上にわたってあつらえの着物を手がける新谷茂代表が絵柄を手描きし、熟練のスタッフが手絞りを担う。どの工程も機械に頼ることは一切ない。「化学染料ならば30分ほどで終わるところが、草木染めでは白からグレーにするだけで3時間かかる」と新谷代表。完成までに20もの工程が必要で手間はかかるものの、そこには手仕事ならではの気品や風合いが漂っている。
巻き方を変えることで、表情を変える点も魅力である。手描き模様のグレー部分を前面に出しカジュアルに着こなしたり、柄を隠して黒の部分を見せ喪の席で身につけたりと、1枚でもいろいろなシーンで使い分けられる。
新谷工芸では、昨年11月にISICOが開催した「石川のこだわり商品フェア」(香林坊大和)や今年2月の「東京インターナショナル・ギフト・ショー」(東京ビッグサイト)に出品するなど、積極的なPRを進めている。商品は大手通販会社の目に留まり、昨年秋からはミセス向けの通販カタログでも取り扱いがスタート。現在、日本各地から注文が届いおり、売れ行きは好調に推移している。
能登のヤシャブシから生まれる味わい
 「黒の装い」は世界農業遺産に選ばれた能登の里山里海の恵みを生かした商品としても注目を集めている。染色の主原料となるヤシャブシは、田畑を開墾したり、林道を切り開いたりするなどし、人が生活を営む里山に数多く自生しており、その実は古くからお歯黒などの染料に用いられてきた。
「黒の装い」は世界農業遺産に選ばれた能登の里山里海の恵みを生かした商品としても注目を集めている。染色の主原料となるヤシャブシは、田畑を開墾したり、林道を切り開いたりするなどし、人が生活を営む里山に数多く自生しており、その実は古くからお歯黒などの染料に用いられてきた。
ヤシャブシは草木染め用の染料として流通しているが、新谷工芸はあくまでも能登産にこだわって、手作りする。それは、味わいある黒を生み出すタンニンが豊富に含まれる種子を余さずに活用するためで、実が開いてしまう10月下旬までに収穫し、乾燥したものを原料としている。色に妥協を許さない姿勢が、ここにも表れている。
長年のデータと技術の蓄積が生んだ工芸品
新谷工芸が「黒の装い」の開発に乗り出したのは2年前からで、土台となったのは長年かけて積み重ねてきた染色データである。「草木染め教室を平成2年に開き、それ以来、能登の多種多様な植物で染めを行い、色合いや耐光性などについて調べてきた」と新谷代表は話し、23年間でデータ収集した植物は250種類にも上る。その中から商品化に適した植物を探り、色調を厳しく見極めていく過程で選んだのがヤシャブシだった。
参考となるデータがあったとは言え、開発のすべてが順風満帆に進んだわけでない。特に苦心したのが、黒やグレーに染め分けたり、模様を作ったりする手絞りの工程である。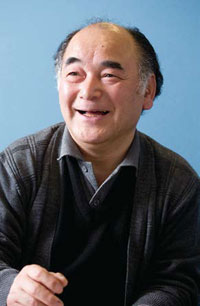 絹の薄い生地に絞りを施すのは新谷工芸としては初めての経験で、長年、草木染めを手がけてきた技術をもとに、染料がしみ込まないよう生地を縫い、食品用ラップを巻く手絞りの方法に何度も改良を重ねていった。
絹の薄い生地に絞りを施すのは新谷工芸としては初めての経験で、長年、草木染めを手がけてきた技術をもとに、染料がしみ込まないよう生地を縫い、食品用ラップを巻く手絞りの方法に何度も改良を重ねていった。
さらに、昨年秋からは機能面の向上を目指し、県工業試験場へ出向いて光や汗による色あせ、摩擦時の生地の傷みを科学的な視点で明らかにし、製造に生かした。その結果、品質は一般に流通する化学染料の製品と変わらないほど高まっている。
新谷工芸では現在、商品ラインアップの充実に乗り出し、ヤシャブシ以外の植物を使った草木染め製品の開発も視野に入れる。能登の里山生まれの新たなファッションアイテムの登場が期待される。
企業情報
| 企業名 | 新谷工芸 |
|---|---|
| 創業・設立 | 創業 昭和57年8月 |
| 事業内容 | 染色加工 |
関連情報
| 関連URL | 関連URLを開く |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.69より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.69 |






