本文
目指すは測量会社の進化形 データ活用型の新事業に活路(2)
明日へのチャレンジ
公共事業の削減で社員数は半分以下に
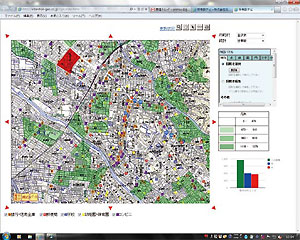 一口に測量と言っても、そのフィールドは大きく地上、空、海上の三つに分けられる。ふだん私たちがよく目にする地上での測量では、道路や鉄道、建築物などを作るための用地を測るほか、緯度や経度、標高の基準となる三角点などの設置も業務に含まれる。空からの測量は、航空機から撮影された写真を基に地形図を作成する作業だ。海上での測量は深浅測量と呼ばれ、船上から精密音響測深機を使って海岸や港湾、ダムの深さを調査する。
一口に測量と言っても、そのフィールドは大きく地上、空、海上の三つに分けられる。ふだん私たちがよく目にする地上での測量では、道路や鉄道、建築物などを作るための用地を測るほか、緯度や経度、標高の基準となる三角点などの設置も業務に含まれる。空からの測量は、航空機から撮影された写真を基に地形図を作成する作業だ。海上での測量は深浅測量と呼ばれ、船上から精密音響測深機を使って海岸や港湾、ダムの深さを調査する。
県内では現在、100社以上の測量会社がしのぎを削っているが、中でも北日本ジオグラフィは陸上だけでなく、空や海からも測量できる技術と実績を有する数少ない企業だ。
とはいえ、測量会社を取り巻く事業環境は厳しく、磯野社長は「石川県の土木工事はピーク時だった平成10年に比べ、4割に減少した」と表情を曇らせる。実際、公共事業が削減される中で同社の売り上げは伸び悩み、以前は70人以上いた社員も半分以下にまで減少した。
 そこで、新たな収益の柱として、期待をかけるのがデータ活用型の事業である。例えば、農地を撮影した衛星画像から米の旨みを左右するタンパク質の含有量を解析し、栽培管理に生かしてもらう取り組みもその一つである。これは平成21年から22年にかけてJA白山に採用され、特別栽培米の付加価値アップに貢献した。
そこで、新たな収益の柱として、期待をかけるのがデータ活用型の事業である。例えば、農地を撮影した衛星画像から米の旨みを左右するタンパク質の含有量を解析し、栽培管理に生かしてもらう取り組みもその一つである。これは平成21年から22年にかけてJA白山に採用され、特別栽培米の付加価値アップに貢献した。
また、農地の地図データにどの田畑でどういった作物が作られたかといった情報を組み合わせ、計画的な農地管理や作物の生産性向上につなげている事例もある。
冒頭で紹介した世帯数ナビもこうしたデータ活用型事業の試みの一環というわけだ。
地図の3次元化を見据え韓国のIT企業を視察
データ活用型の事業を模索する磯野社長は今年8月、新たな可能性を求めて韓国・大邸(てぐ)広域市で開かれた商談会に参加した。大邸はIT産業の盛んな韓国第4の都市で、商談会への参加は、大邱デジタル産業振興院と9年前から交流するISICOが橋渡しした。
 磯野社長が商談を持った企業の一つは3 次元コンピュータ・グラフィックスを駆使したリアリティの高い地理情報システム(GIS)を構築するEGIS 社である。磯野社長によれば、「日本では今のところ地図の3次元化に関するニーズは高くない」そうだが、韓国では既に景観や防災のシミュレーション、観光案内など、幅広い用途に利用されており、「今後、地図データをもっと有効に活用するための選択肢にしていきたい」と話す。
磯野社長が商談を持った企業の一つは3 次元コンピュータ・グラフィックスを駆使したリアリティの高い地理情報システム(GIS)を構築するEGIS 社である。磯野社長によれば、「日本では今のところ地図の3次元化に関するニーズは高くない」そうだが、韓国では既に景観や防災のシミュレーション、観光案内など、幅広い用途に利用されており、「今後、地図データをもっと有効に活用するための選択肢にしていきたい」と話す。
このほかにも、避難場所だけでなく、災害弱者と言われる高齢者や障害者の所在を地図上に示し、地震や洪水が起きた時の救助に役立てる福祉防災地図など、アイデアはまだまだ広がる。「目指すは測量データや地図データを解析したり、活用したりすることで民間企業や地方自治体の抱える課題を解決する地理空間情報コンサルタント」と力を込める磯野社長。測量会社の新たなビジネスモデルの構築に向け、チャレンジが続く。
企業情報
| 企業名 | 株式会社 北日本ジオグラフィ |
|---|---|
| 創業・設立 | 創業 昭和27年4月 |
| 事業内容 | 地上測量、空中写真測量、深浅測量、地理空間情報コンサルタント |
関連情報
| 関連URL | 関連URLを開く |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.66より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.66 |






