本文
【巻頭特集】デザインや商品開発の効率アップへ 加賀友禅の図案を画像データ化 ~毎田染画工芸
「デジタル化設備導入支援事業」が生産性向上や事業拡大を後押し
ISICOのデジタル化設備導入支援事業は、AIやIoT、RPA、クラウドサービス等を活用し、生産性向上や事業拡大に挑戦する中小企業を資金面でバックアップする制度で、今年度は121社を採択した。巻頭特集ではこの中から2社の取り組みにスポットを当てる。
90年分の資産を有効活用したい
 毎田染画工芸は1932年の創業以来、三代にわたって伝統の技を受け継ぐ加賀友禅の工房だ。加賀友禅には13から15の工程があり、近年は分業化が進んでいるが、同社では図案の作成から彩色、仕立てに至るまで、一貫制作できる体制を整えている。
毎田染画工芸は1932年の創業以来、三代にわたって伝統の技を受け継ぐ加賀友禅の工房だ。加賀友禅には13から15の工程があり、近年は分業化が進んでいるが、同社では図案の作成から彩色、仕立てに至るまで、一貫制作できる体制を整えている。
同社がデジタル化設備導入支援事業に採択され、導入したのが大型スキャナーだ。このスキャナーを使い、加賀友禅の図案を画像データとして保管し、デザイン業務の効率化や商品開発に役立てるのが狙いだ。
 「加賀友禅の制作にあたり、私たちはまず、自然の美しさやそこから得た感動を基にイメージを膨らませ、原寸大の図案を紙に描きます。工房には祖父が作家活動を始めた90年前から図案を紙のままストックしています。ほとんど有効活用できていなかったのですが、画像データとして閲覧、検索が可能な状態にしておけば、仕事のスピードアップにつながると考えました」。
「加賀友禅の制作にあたり、私たちはまず、自然の美しさやそこから得た感動を基にイメージを膨らませ、原寸大の図案を紙に描きます。工房には祖父が作家活動を始めた90年前から図案を紙のままストックしています。ほとんど有効活用できていなかったのですが、画像データとして閲覧、検索が可能な状態にしておけば、仕事のスピードアップにつながると考えました」。
導入のきっかけについてこう話すのは、三代目の毎田仁嗣さんである。毎田さんは約30年前の大学生時代からデジタル技術を活用したデザイン制作に取り組んでおり、今回の試みもその一環だ。
時代に合わせて過去の図案をアレンジ
導入した大型スキャナーは、最大でA0判(841×1189ミリ)まで読み取りが可能だ。活用頻度が高そうな図案は、画像編集ソフトを用いて、どれだけ拡大しても品質が変わらないベクター画像に変換の上、保管する。ファイル名には、後で検索しやすいよう、図案に描かれている草花や鳥の名前などを付けておく。
データを活用できるタイミングは主に二つある。一つは着物の図案作成時だ。加賀友禅のデザインは、草花や風景のスケッチ、撮影から始まり、とても時間の掛かる仕事だ。毎田さんによれば、過去の図案をそのまま使うことはないが、新たな図案を作成する際の参考にする、あるいは今の時代に合わせてアレンジして用いるケースはあるそうで、この際、画像データ化して簡単に検索、閲覧できるようにしておけば、デザイン作業が効率よく進むケースがあるという。
仮案を素早く作り受注機会を拡大
また、着物以外の商品開発時にも画像データを有効活用する。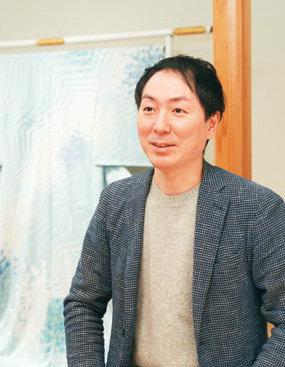
同社では菓子のパッケージや室内装飾品などをデザインする仕事も多い。問い合わせをもらった段階で、どんなデザインを提供できるのか、過去の図案データの一部を組み合わせるなどして仮案を作成し、素早くクライアントに提示できれば、イメージの共有に役立ちビジネスチャンスを逃さず受注できる可能性が高まる。
また、受注後にあらためてオリジナルの図案を作成する場合でも、過去の図案の一部をデータとして活用できれば、納期短縮につながる。
「提案までのスピードはうまくいけば半分に短縮できます。和のデザインは熟練者でなければ難しいが、画像データを活用すれば、パソコンのスキルがある若手でもある程度のデザイン作業ができるようになるのもメリットです」(毎田さん)。
職人の仕事を創出し後世に技術を継承
加賀友禅は結婚式やパーティーなどに合わせて新調されるフォーマルな着物である。着物離れに加え、コロナ禍で需要が減る中、事業を継続、発展させていくには、着物以外の用途を伸ばしていくことが重要だ。
「考え方や制作の中心はあくまで着物ですが、それ以外に加賀友禅の魅力を楽しんでもらえるものを作っていけば、経営が安定し、社会環境の変化に強い会社になれるので、さらに強化していきたいと考えています」。毎田さんはこう話し、現に着物以外の分野の売り上げが着々と伸びている。
 スカーフやアクセサリーなど、自社商品も展開し、一昨年に発売したマスクは累計販売数が2万枚に達する人気となっている。このマスクにも、かつて着物に描かれた絵柄がワンポイントに添えられており、デジタル化された過去の図案が活用できるシーンはまだまだ増えそうだ。
スカーフやアクセサリーなど、自社商品も展開し、一昨年に発売したマスクは累計販売数が2万枚に達する人気となっている。このマスクにも、かつて着物に描かれた絵柄がワンポイントに添えられており、デジタル化された過去の図案が活用できるシーンはまだまだ増えそうだ。
毎田さんが着物以外の分野に注力するのは、これによって職人の仕事を創出できれば、技術の継承に役立つと考えているからだ。また、確かな成長戦略を確立できれば、作家や職人を目指す人材を呼び込むことにもつながる。
紙の図案は数千枚あり、スキャナーで読み込む作業が順次進んでいる。やがて構築されるデータベースは言ってみれば宝の山であり、使い方次第で、加賀友禅の可能性を大きく広げてくれるに違いない。
企業情報
| 企業名 | 毎田染画工芸 |
|---|---|
| 創業・設立 | 創業 1932年 |
| 事業内容 | 加賀友禅、友禅小物などの制作 |
関連情報
| 関連URL | 情報誌ISICO vol.121 |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.121より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.121 |






