本文
いしかわ版!DX超入門 あいまいな理解で間違ったアプローチをしないために
持続的成長へ変化のチャンス! 中小企業DX化&人材戦略セミナー
ISICOはDXの観点から見た人材戦略セミナーをオンライン開催し、県内企業の経営者らが参加しました。全3回のうち2月22日の第1回では(株)ロードフロンティア(東京都)代表取締役の並木将央氏が、DXが求められる理由や導入のポイントについて解説しました。セミナーの内容をダイジェストで紹介します。
優位性を確立するトランスフォーメーション
「 DX」とはデジタル・トランスフォーメーションの略で、直訳するとデジタルを使ってトランスフォーメーション、すなわち変革することを意味します。
DX」とはデジタル・トランスフォーメーションの略で、直訳するとデジタルを使ってトランスフォーメーション、すなわち変革することを意味します。
ここで言う変革とは、新しい製品・サービスで優位性を確立することです。つまり、単なるデジタル化では、DXにならないわけです。
DXに至るデジタル化には3つのフェーズがあります。最初がツールを使用して特定業務をデジタル化するデジタイゼーション。次が、業務フローやプロセスをデジタル化するデジタライゼーション。そして、ビジネスモデル自体をデジタルなものに変革するDXです。
こう聞くと、デジタルによる効率化や省力化はDXにあたらないのかという疑問が湧いてくると思います。まさしく疑問の通り、効率化も省力化もDXの目的ではありません。
1990年代初頭、DXとよく似た「BPR(※1)」が推し進められました。BPRとは「業務本来の目的に向かってビジネスプロセスを見直し、業務フローや情報システムなどを抜本的に再設計する」という考え方です。
一見するとBPRとDXは似た概念に思えますが、はっきりと違いがあります。まず、BPRの目的が自社のための効率化・省力化であるのに対し、DXの目的は顧客のための価値創造にあります。アプローチの手法も違い、BPRは見えている課題に対してアプローチするのに対し、DXは潜在的な課題に対してアプローチします。
こうした、BPRとDXの違いを押さえていないと、ベンダーにDXの相談をしても、実際はBPRになってしまいがちなので注意が必要です。
成長時代が終わり大量消費も終局に
では、なぜ今DXが必要なのでしょうか。簡潔に言えば、日本の人口が2006年の1億2,774万人をピークに減少局面に突入したことで、その後の内需縮小が確実になり、大量生産・大量消費の時代が終わりを迎えたからです。
人口が増え続けていた昭和期は、労働者も消費者も増え続けることで市場が活性化し、高所得化が続くまさに成長社会でした。この成長社会では、物質的な不足や不便が数多く存在し、「不」を解消することで多くの企業が成長しました。
一方、人口減少後の成熟社会では物やサービスがあふれ、「不」がありません。それどころか、成熟社会では価値観が多様化して複雑になり、将来の予測が困難になる、まさに「VUCA(※2)」時代です。
こうした成長から成熟への時代の変化に対応し、働き方にもビジネスにもパラダイムシフトを起こすために、DXが求められているのです。
ツールは豊富でも価値を生むのは人
さて、DXはさまざまなデジタル技術を用いて進められます。代表的なものをいくつか紹介しましょう。
まず、AIです。日本語では人工知能と訳し、具体的には人間の思考プロセスと同じような形で動作するプログラム全般を指します。能力によって5つのレベルが設けられていますが、レベルにかかわらずAIの活用で押さえておきたいのは、AIは限定した環境下での特定動作が得意だということです。また、現在AIの導入は経済産業省の「ものづくり補助金」に採択されやすいのもポイントでしょう。
RPAも、ウィンドウズ11からマイクロソフトのRPAツール「パワーオートメイト」が標準搭載になり、コストゼロで使えるようになったことがホットな話題です。ただし、RPAは抜本的な業務改革に直結しないことに留意が必要です。作業時間が短くなることで作業内容や手順の見直しが先送りになったり、古いシステムの更新の妨げになったりすることがあるからです。
モノがインターネット経由で通信するIoTは、日々膨大に生成されるビッグデータの収集に向いています。IoTでデータを集めてクラウドに集約し、AIが分析するというビッグデータの活用方法がすでに確立しています。
とはいえ、ビッグデータを分析して、意思決定の基になる情報を蓄積したとしても、価値を生み出す材料となる知識や実際に価値を生み出す知恵は人間が担うことに変わりありません。
ITリテラシーよりビジョンが重要
DXを推し進めるにあたって、よくある失敗が単にITリテラシーの高い社員に任せてしまうことです。デジタルツールはあくまでも手段でしかないので、これらを使ってどう変わりたいかのビジョンをリーダーが示さなければなりません。
DXに必要な人材と言えばプログラマーのイメージが強いかもしれませんが、実際はさまざまな人材が求められます。例を挙げると、(1)DXを主導するリーダー(2)DXの企画・立案・推進を担うビジネスデザイナー(3)システムを設計するアーキテクト(4)データ解析に精通するデータサイエンティスト(5)システムのユーザー向けデザインを担当するUXデザイナー(6)システムの実装やインフラ構築を担うプログラマーなどです。
これら6つの領域を1人でカバーすることはできません。(3)~(6)は外注に任せられても、(1)(2)は基本的に社内の人間が務めるしかなく、中小企業であれば社長もしくは事業部長が担うべき領域です。
しかし、日本では(1)(2)が、圧倒的に不足しています。不足の理由は、「成果が見えることしかやらない」という企業の姿勢が人材育成の妨げになっているからです。その一方で、(1)(2)の充足は既存人材の登用が8割を超えており、社内での育成が必要なのに育っていない現状があります。こうした人材不足の解決には、「成果が見通せなくても失敗を恐れずトライする」姿勢への転換が必要です。
推進部門で変わる進み方と本質
DXを推進する部門を組織のどこに置くかも考えなければなりません。既存部門に任せるなら企画部門かIT部門か、新設するなら全社支援型か独立型かで、DXの浸透に特徴が表れるからです。
例えば、企画部門は試行的な取り組みがしやすく、IT部門なら既存業務の効率化が進みやすい傾向にあります。とはいえ、DX推進部門のポジショニングは、「どこが良いか」を考える以上に、会社として「どうしたいか」「いつまでに終わらせるか」という経営戦略が重要になります。
DXの本質は人の活性化です。デジタルを導入して人を活性化させることによって、活性化した人が付加価値を作り、付加価値がビジネスを支え、会社の成長につながります。DXに正しくアプローチするためにも、どう変わりたいか、どう変わるべきかのビジョンを持つことが大切なのです。
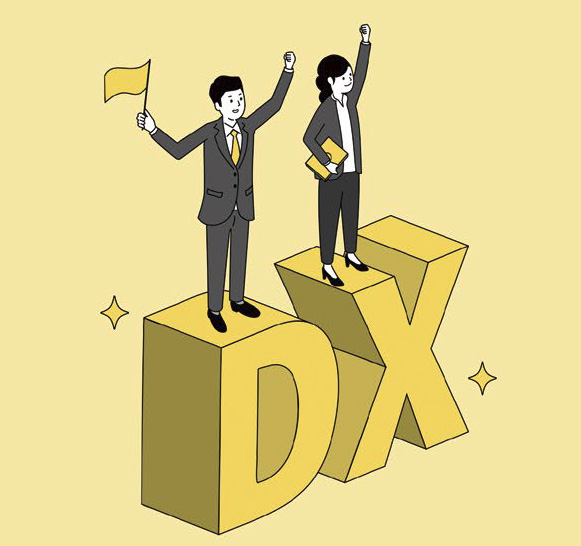 ※1 BPR(Business Process Reengineeringの略)
※1 BPR(Business Process Reengineeringの略)
※2 VUCA…社会やビジネスにおいて将来の予測が困難になっている状態を示す造語。
Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字
企業情報
| 企業名 | 公益財団法人 石川県産業創出支援機構 |
|---|---|
| 創業・設立 | 設立 1999年4月1日 |
| 事業内容 | 新産業創出のための総合的支援、産学・産業間のコーディネート機関 |
関連情報
| 関連URL | 情報誌ISICO vol.122 |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.122より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.122 |






