本文
CASE02 EVや産業用ロボット市場の開拓目指し事業再構築補助金で新たな加工機を導入 ~実川鉄工(株)
チャンスをつかみミライをひらく
実川鉄工は昨年8月、事業再構築補助金を活用し、精密穴開け加工の専用機・治具ボーラーを導入した。補助金の申請にあたっては、ISICOが認定支援機関としてサポートした。同社では、この治具ボーラーを使って、新たにEV(電気自動車)関連の受注を獲得したほか、今後はロボット分野へも業容を拡大しようと商談を進めている。
一貫生産体制と高精度の加工に強み
実川鉄工が主力として製作しているのは、自動車関連の治具である。治具とは金属などを加工する際に、加工の対象となる材料(ワーク)を工作機械に固定するための道具を指す。同社の場合、具体的にはエンジンのシリンダーヘッドやシリンダーブロック、ミッションケース、クランクシャフトといった部品を加工する際に必要となる治具を作っている。
正しい位置にワークが固定されていなければ、たとえ精度よく加工したとしても、仕上がりの寸法に狂いが生じてしまう。そのため、治具そのものにも100分の1ミリ単位の高い精度が要求される。
 治具は少なくて100個程度、多いものでは200個ほどの部品から構成され、同社では、さまざまな金属材料を使って、これらの部品を加工するのはもちろん、組み立てや調整、配管、試運転までを一貫して自社で手掛けられる体制を整えている。
治具は少なくて100個程度、多いものでは200個ほどの部品から構成され、同社では、さまざまな金属材料を使って、これらの部品を加工するのはもちろん、組み立てや調整、配管、試運転までを一貫して自社で手掛けられる体制を整えている。
これに加え、年間を通じて室温を一定に保った恒温室と3次元測定機を備え、精度を保証した上で納入している点も大きな強みとなっている。
精度や生産性が向上大きなワークも加工可能に
そんな同社が事業再構築補助金を活用して導入したのがCNC(コンピューター数値制御)治具ボーラーだ。
治具ボーラーとは高精度で穴開け加工するための専用機だ。先に述べたように、治具の役割は正しい位置にワークを固定することであり、固定する際に使われる穴にも高い精度が求められる。

従来、同社では要求される精度を満たすため、工具の移動量や移動速度を手動で設定する汎用治具ボーラーでまず加工し、その後、NC横中ぐりフライス盤で仕上げていたが、工数が多く、時間がかかることがネックになっていた。CNC治具ボーラーはこれらの加工を1台で完結できるため作業効率がアップし、より高い精度にも対応が可能となった。
また、従来は長辺が1,000ミリまでの範囲でしか加工できなかったが、新設備の導入によって、最大で長辺1,500ミリまでの範囲を加工できるようになったことも大きなメリットだ。
こうした長所を生かして、同社では新たにEV用のモーターカバーの製造時に使われる治具の製作を受注した。
将来的には、自動車工場などで活躍する産業用ロボットの部品の受注を目指し、商談を進めている。
生き残っていくためエンジン以外の領域へ

同社がCNC治具ボーラーを導入したのは、エンジンに依存した経営体質からの脱却が狙いだ。
「コロナ禍によって、中国での自動車生産に急ブレーキがかかったことで、2020年の売り上げが大きく落ち込んだ。さらに、脱炭素化の流れにより、ガソリンエンジン車に代わって、EVの普及が見込まれ、この先、生き残っていくためには、何か手を打ってエンジン以外の領域に仕事を広げなければならないと考えた」(山田光孝社長)。
そこで、これまで培ってきた精密加工のノウハウを生かせる分野として、山田社長がターゲットとしたのがEVや人手不足感が強くなる中でニーズの増加が見込める産業用ロボットだった。
とはいえ、EVではエンジン用よりも大きなサイズの治具が必要とされる。治具に比べてロットの多い産業用ロボットを手掛けるには、生産性の向上も必須だ。そこで導入したのが、CNC治具ボーラーだったというわけだ。
書類作成に専門家が助言 1回目の申請で見事採択
補助金の申請にあたっては、ISICOが運営する「石川県よろず支援拠点」が書類作成についてアドバイスし、見事1回目で採択を勝ち取った。
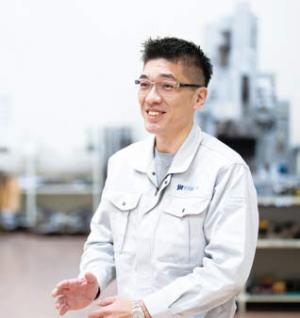 「申請書を書くのは初めてで、何をどのように説明すべきか分からなかったが、的確な指導のおかげで、市場のニーズや競合他社に対する優位性、費用対効果などについて、審査員に伝わるように分かりやすくまとめることができた。書類作成を代行してくれるコンサルタントは有料だが、よろず支援拠点は無料で相談に乗ってくれて助かった」(山田社長)。
「申請書を書くのは初めてで、何をどのように説明すべきか分からなかったが、的確な指導のおかげで、市場のニーズや競合他社に対する優位性、費用対効果などについて、審査員に伝わるように分かりやすくまとめることができた。書類作成を代行してくれるコンサルタントは有料だが、よろず支援拠点は無料で相談に乗ってくれて助かった」(山田社長)。
エンジン関連の受注も約1年前から回復し始め、これからは既存の分野に加えて新分野での仕事を増やし、会社の成長につなげていく計画だ。従来の顧客が取引先となるEVと違って、これまで付き合いのない新規顧客の開拓が必要となる産業用ロボット分野ではまだ成約実績はない。しかし、山田社長は「必ず伸びる市場なので、慌てず粘り強く商談して実績を増やしていきたい」と意欲をみなぎらせている。
企業情報
| 企業名 | 実川鉄工 株式会社 |
|---|---|
| 創業・設立 | 創業 1957年2月 |
| 事業内容 | 各種専用機・治具製作、精密機械加工 |
関連情報
| 関連URL | 情報誌ISICO vol.126 |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.126より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.126 |






