本文
「かほく工業試験場」の受託検査サービスが新たな収益源に ~TANIDA(株)
サキドリ
高い技術力で航空機エンジン用の鋳物などを製造するTANIDA。これまで培ってきたノウハウを生かして事業化した、製品の形状や品質を確認するための検査の受託も順調に売り上げを伸ばしている。
航空機エンジン部品が売り上げの約3割に
 アルミ・マグネシウム鋳物の製造・加工を手掛けるTANIDAは、右肩上がりの成長を続けている。
アルミ・マグネシウム鋳物の製造・加工を手掛けるTANIDAは、右肩上がりの成長を続けている。
その一因は、事業分野の戦略的な絞り込みにある。現在、同社の売り上げの約5割を占めるのが伸長著しい半導体を製造する装置の部品だ。付加価値が高く、参入障壁が高い航空機エンジン部品も好調で、2009年の取り組み開始から約15年をかけ、今では売り上げの約3割を占める柱に成長した。
同社の技術力は折り紙付きだ。「差圧鋳造」と呼ばれる欠陥を大幅に抑える独自技術もその一つである。また、鋳造にとどまらず、機械加エや溶接、表面処理、組み立てなどをワンストップで提供する一貫生産体制を構築し、総合的なソリューションを提供。高精度の3Dプリンターで鋳型を作製する技術を確立し、試作期間を従来の半分以下に短縮できることも、海外の大手航空機メーカーや航空宇宙部品サプライヤーから受注を呼び込むPR材料となっている。
績み上げたノウハウ生かし製品の形状や品質を確認
 生産量が増えるのに伴い、金沢市内の工場が手狭になったことから、2022年にかほく市に新工場を建設し、本社機能と機械加工部門、検査部門を移設した。
生産量が増えるのに伴い、金沢市内の工場が手狭になったことから、2022年にかほく市に新工場を建設し、本社機能と機械加工部門、検査部門を移設した。
新工場の稼働に合わせ、「かほく工業試験場」と名付けてスタートしたのが、受託検査サービスである。これは寸法や硬度、耐圧性、組織、表面欠陥、清浄度など、製品の形状や品質を確認するための検査業務を提供するサービスだ。破壊検査はもちろん、非破壊検査にも対応する点が強みで、例えば最大で直径1メートル、長さ1.3メートルの試料を検査できるX線検査システムは全国有数の設備だ。
航空機や半導体製造装置の部品を製造するには、厳格な品質管理が求められる。同社ではこれまで自社製品の品質保証のために必要な機器をそろえ、検査技術に磨きをかけてきた。新サービスには、こうして積み上げてきた高度なノウハウが生かされているというわけだ。
サービス開始以降、大型部品を1工程で鋳造する技術の評価や数多くの部品で構成される製品の内部検査など、自動車関連業界を中心に引き合いが増えている。駒井公一社長は「わずか数年で売り上げの4%を占めるまでに成長し、新規事業としては順調なスタートを切った」と手応えを話す。
受託検査がきっかけで鋳造の仕事を受注するケースもあれば、その逆もあり、新事業と既存事業がうまくシナジーを作り出している。
ISICOの継続支援が技術の高度化を後押し
 受託検査サービスの立ち上げにあたっては、ISICOのサポートも後方支援となっている。
受託検査サービスの立ち上げにあたっては、ISICOのサポートも後方支援となっている。
というのも、同社ではアルミ合金やマグネシウム合金の熱処理、溶接、非破壊検査(蛍光浸透探傷試験、デジタルX線検査)などの分野で、航空機部品の製造や検査に必要とされる国際認証「Nadcap」の取得に先立ち、ISICOの専門家派遣制度を活用してアドバイスを受けた。このNadcapの認証が受託検査サービスの信頼性を担保しているのだ。そして、認証取得後もISICOの成長促進高度アドバイザー活用事業を使って、こうした技術の研さんに励んでいる。
「そもそもこれらの分野は専門家が少ない上、独自に勉強しているだけでは技術の高度化にも限度がある。継続的な支援を受けることができて、本当に助かっている」と駒井社長は話す。
チタンの鋳造とUAVエンジン開発に挑戦
今後の成長戦略として同社では、本業である鋳造技術のさらなる革新と、これまで培ってきた技術やノウハウを生かした新分野への挑戦を計画している。
一つはチタンの鋳造だ。チタンは鉄よりも軽く、アルミやマグネシウムよりも強度や耐熱性に優れるが加工が非常に難しい。この技術を確立することで、航空機市場などでさらなる受注拡大を目指す。
もう一つは、UAV(無人航空機)向けエンジンの開発だ。イギリスのUAVメーカーと協力し、既に実証機を完成させテストに取り組んでいる。ガソリンよりも扱いやすいジェット燃料や軽油で作動する点が特長で、国際展示会でも注目を集めた。将来は災害現場や離島への輸送用などとしての活用を視野に入れる。
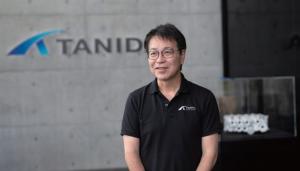 本社工場のスペースが既に埋まっているため、2027年春には隣接地に新工場の建設を予定しており、受託検査サービスを含め、新規事業の商機拡大につなげる考えだ。
本社工場のスペースが既に埋まっているため、2027年春には隣接地に新工場の建設を予定しており、受託検査サービスを含め、新規事業の商機拡大につなげる考えだ。
「将来的には売上高を現在の40億円から100億円にまで引き上げたい」と意欲を示す駒井社長。同社の成長戦略の行く末にこれからも注視したい。
企業情報
| 企業名 | TANIDA株式会社 |
|---|---|
| 創業・設立 | 設立 1962年5月 |
| 事業内容 | 軽金属の鋳造、機械加工とその付帯業務および海外輸出入業務、受託検査業務など |
関連情報
| 関連URL | 情報誌ISICO vol.141 |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.141より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.141 |






