本文
仲間の支援を受け、酒造り再開を決意 伝統的なかまどを修復し、輪島の味を全国へ ~(株)白藤酒造店
One Step
令和6年能登半島地震で被災しながらも、試練を乗り越え、明日への一歩を踏み出した地元企業の奮闘ぶりを紹介します。
県内外の酒蔵が支援
 江戸時代末期から酒造りを続け、銘酒「奥能登の白菊」で知られる白藤酒造店。全国にファンを持つこの酒蔵も、能登半島地震で深刻な被害を受けた。
江戸時代末期から酒造りを続け、銘酒「奥能登の白菊」で知られる白藤酒造店。全国にファンを持つこの酒蔵も、能登半島地震で深刻な被害を受けた。
店舗や事務所を含む複数の建物が全壊・半壊した。蔵は倒壊を免れたが、米を蒸すためのかまどの基礎部分に亀裂が入って使用不能に。さらに、タンクが転倒・破損し、日本酒の元となるもろみの大半が流出してしまった。
白藤酒造店の苦境に真っ先に手を差し伸べたのは、全国の酒蔵仲間たちだった。1月4日に山形県の蔵元が支援物資を携えて駆けつけ、13日には山形県と福島県の蔵元、15日には宮城県の蔵元がタンクローリーとポンプを使って、残ったもろみを丁寧にくみ上げた。このもろみを羽咋市と宮城県の酒蔵が引き継ぎ、日本酒に仕上げた。
また、羽咋市と長野県の酒蔵がそれぞれ、白藤酒造店で保管していた酒米を用いて、同店の造り方に沿って醸造を代行した。白藤喜一社長は「商品として世に出せたのは本当にうれしく、仲間の助けが、もう一度酒造りを目指す大きな原動力となった」と振り返る。
災害前の出荷量を目標に
 白藤酒造店が復旧の柱として力を入れたのが、直径1.5メートルの伝統的な直火式かまどの修復だった。現在の主流であるボイラー式に比べて熱効率は低いが、同店にとっては酒造りの精神の象徴であり、なくてはならないものだった。
白藤酒造店が復旧の柱として力を入れたのが、直径1.5メートルの伝統的な直火式かまどの修復だった。現在の主流であるボイラー式に比べて熱効率は低いが、同店にとっては酒造りの精神の象徴であり、なくてはならないものだった。
基礎造りからやり直し、秋田県と岩手県のかまど職人を招いて組み上げた。同時にタンクの新調も進め、今年3月、1年3カ月ぶりに自社蔵での仕込みを開始した。
蔵人5人のうち3人が被災を機に輪島を離れたこともあり、例年10種類前後仕込んでいた酒を4種類に絞った。その中には、輪島産の酒米のみを使った銘柄も含まれている。「地域の復興を願い、今年の酒には特別な思いを込めた」と白藤社長は話す。
酒造りは再開できたものの、事務所はプレハブのままで、店舗の再建も見通しが立っていない。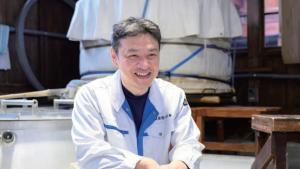 そこでISICOに相談し、補助金の申請に向けた手続きを進めている。白藤社長は「ありがたいことに、私たちのお酒を待ち続けてくださる方が全国にいる。なんとか期待に応えたい」と希望を語り、出荷量を震災前の水準に戻す体制づくりを目指している。
そこでISICOに相談し、補助金の申請に向けた手続きを進めている。白藤社長は「ありがたいことに、私たちのお酒を待ち続けてくださる方が全国にいる。なんとか期待に応えたい」と希望を語り、出荷量を震災前の水準に戻す体制づくりを目指している。
企業情報
| 企業名 | 株式会社 白藤酒造店 |
|---|---|
| 創業・設立 | 創業 1700年代中ごろ |
| 事業内容 | 日本酒の製造・販売 |
関連情報
| 関連URL | 情報誌ISICO vol.141 |
|---|---|
| 備考 | 情報誌「ISICO」vol.141より抜粋 |
| 添付ファイル | |
| 掲載号 | vol.141 |






