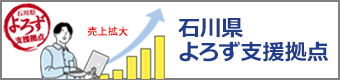本文
小松産の米・白山の伏流水・金沢酵母こだわリ抜いた酒造りが神泉の真骨頂 東酒造(株)
↵
東酒造株式会社

「神泉」のブランドで知られる小松市の酒蔵・東酒造株式会社。万延元年(1860年)の創業から今日まで、「地酒は土地の文化」を標榜し、163年の歴史を刻む老舗の7代目・東祐輔代表取締役に、コロナ禍の厳しい環境下を乗り越え、次代につなぐ、東酒造にしかできない、美味しい酒を追求する、こだわりの酒造りに込める胸の内を披歴いただいた。
限られた石高を地元のお客様最優先で販売
東酒造の特徴は何といっても国登録有形文化財に指定されている地元小松の観音下石で造られた石造りの酒蔵。酒蔵は一般的には木造が主流で、石で造られた酒蔵は全国的にも珍しい。もう一つは、先代の時代から地元小松産のお米を原料に酒造りに取り組んできていること。当時は、地元小松産の米で酒造りをするのはナンセンスと言われた。そんな中、先代が農協に直談判を重ね、無理を通し小松産の米だけを仕入れる。十年余り前から6代目が米農家と一緒になって、小松で山田錦の栽培にチャレンジし、当初はなかなか生育が難しく苦労の連続だったが、その後は順調に栽培できるようになり、地元小松産の米で酒造する精神をしっかりと受け継いでいる。さらに、同蔵の酒は県外では販売していない。自社蔵で製造できる量は300石、頑張っても350石が限界のため、無理して県外に出すよりも、地元のお客さんを大事にすることが得策との考え。東京で買えないお酒ということがある意味付加価値にもなっている。



地元産コシヒカリ「蛍米」で醸造した「蛍舞」ブランドで新規開拓
兵庫県産と小松産の山田錦、どちらも山田錦ではあるが、風土の違いからお酒になった時の癖が異なる。多少造りにくさはあるものの、その癖さえ掴めば美味しいお酒ができる。山田錦の稲穂は通常のお米より背が高く、風に弱いため、小松の山間部の風の影響を受けにくい土地で栽培されている。かつては、日本酒をコシヒカリで造ることはしないが、同社のポリシーでもある地酒は土地の文化を実践すべく、小松産のコシヒカリ「蛍米」でも醸造している。地元のお米を使った酒造りに徹し、近年はその努力が実を結び評価が高まっている。蛍米で醸造を始めて10年の節目に、甘みのある女性向きの新世代の日本酒「蛍舞プレシャス」《純米吟醸》を商品化。初年度は800本製造して即完売し、令和5年度は1600本製造し、ほぼ完売状態の人気商品に。神泉は伝承と伝統を守った辛口のザ日本酒の酒造りに徹する一方で、蛍舞は若い世代とりわけ女性の新しい顧客層を開拓していけるような新日本酒と位置づけ、従来の日本酒は匂いが苦手、アルコール度数が強い等々の理由で敬遠していた世代に、日本酒も美味しいねと知ってもらうきっかけになる酒造りを目指している。日本酒が売れないと言うのではなく、日本酒メーカーとして、現在の需要に合わせた飲みやすい新しい日本酒を開発していく必要性を痛感しているからこその蛍舞なのだ。従来の神泉ファンが蛍舞を飲むと、これは神泉じゃないとなることから、ブランド名を敢えて変えている。

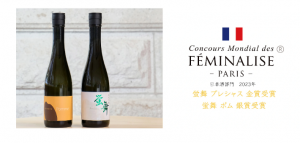
杜氏の勘頼りから化学的な酒造りに進化
かつては東酒造の酒造りにおいても能登杜氏の役割は大きかったが、近年は杜氏の高齢化が顕著なため、現在は東酒造の社員が杜氏の役割を引き継いでいる。昔の酒造りは杜氏の勘や経験に頼るところが大であったが、現在の酒造りは実はとても化学的になっている。新しい造り方が次々と編み出され、1年1年その進化は目まぐるしい。従来からの辛口だけでなく、甘口や酸味のある酒など、どんな風味も自在に創り出せる時代。消費者がそのお酒をどんな場面で、どんな料理と合わせて楽しむのかを社長が考え提案するお酒を新しい方法で造っている。昔からの酒造りは、米・米麹・水を濾したもの、これを守れば日本酒。この考え方が長年続いてきていたが、この10年あまりの間で日本酒の造り方が激変している。かつてのお酒の味は、どの酒米と酵母を使うかで方向性がほぼ決まったが、今は仕込み方が多彩になり、醸造法の間隙を縫うようないろんな方法があり、どんな味付けにするかを考えながら化学的に醸造していくのが新しい時代の酒造りなのだという。


社員のユニークな発想で生まれる新しい酒
同社の「蛍舞プレシャス」という甘口のお酒は、なんとお酒が飲めない社員が造った商品。毎年、チャレンジタンクを1つ設定し、社員のユニークな発想を形にする酒造りに挑んだ中の一つ。もちろん1年限りでなくなる商品もあれば、人気があれば蛍舞プレシャスのように定番商品になるものも生まれている。現代の杜氏は、この酵母は何を欲しているか、酸素が欲しいのか、アルコールが出過ぎて水が欲しいのか、温めて欲しいのか、それを温度管理された数字、日本酒度、アミノ酸度などを全て調べ、菌が元気か弱いかを数字から見てとる。同じ15度の温度でも、上がってきての15度か、下がってきての15度なのかを分析しながら、醪の状態を見ながらいま必要なものを提供していく。お酒を造るというより菌を育てていく酒造り。昔のような杜氏たちが泊まり込みで、夜中に何度も見に行くような時代ではなくなり、社員は朝7時に出社し、夕方5時に帰宅する働き方改革が実践され、それでもいいお酒ができる時代が到来している。


ターゲットを絞った酒造りで各賞にチャレンジ
毎年さまざまな日本酒にまつわる賞を受賞している神泉では、この賞にはこういうお酒が合うだろうとターゲットを絞り、それに向けて酒造りを行っていることもあり、受賞率は約5割と高い。例えば、「蛍舞プレシャス」が受賞したフェミナリーズという大会は、ワインの大会に数年前から日本酒部門ができ、審査員が全員女性であることから、女性向けの商品を開発したという経緯がある。クラマスターになるとソムリエが審査員のため、淡麗辛口タイプの酒の受けがよく、そうしたお酒を造って出品している。受賞を逃した商品については、どこがダメだったのかを細部にわたって検証し、リベンジに向けた酒造りを再スタートする。このようにいろんな賞に合った酒造りにチャレンジすることで、社員の士気高揚にもつながっている。造れる量は限られるものの、東社長が好きな酒造りをモットーに、自身が好む金沢酵母オンリーでやってきて、お米の長所を引き出す近代的な酒造りを実践し、数々の賞を総なめにしてきている。


売上第一から利益第一に舵を切る
「コロナ禍になって、自社の商いについてかなり考えさせられました。」と東社長は述懐する。緊急事態宣言が出された時には売上が3分の1に激減し、飲食店が閉まり、人が集まる結婚式や祭りのような祝い事がなくなり、家で飲みなさいと言われても、家で高いお酒は飲まない等々マイナス材料ばかり。令和5年に入り回復してきたものの、販売数量が増えても利益が出ない状況に直面する。何故忙しいのに利益が出ないのか、それまで売上重視でやってきていたが、コロナ禍を経験し、利益重視に考え方を転換する。会社を存続させるためにいかに利益を出すか、儲からないからと値上げするのは明確な理由がないと消費者に納得してもらえない。同社のベストな商いの内訳は、卸3割、小売3割、自社3割、海外1割の比率であるが、コロナ禍になって消費者が酒屋へ行かなくなり、同社にも来なくなり、卸が扱う大型量販店の比率が高まってきている。数量が増えるのはありがたい反面、卸のウエイトが高まると利幅が少ないため、忙しさの割には利益が出ないのだ。



日本酒の美味しさ、楽しさを提案
コロナ禍が明けたものの、やはり卸のウエイトが高止まりで、小売りは減ったまま、その一方で金沢駅等でのお土産品の売れ行きが伸びてきている。神泉のお酒は毎年のように多くの賞を受賞しているおかげで、試飲をした方の購入する確率は8割と高い。海外での人気も徐々に高まってきていて、全体の15%が輸出向け。従来からの神泉ファンが納得する日本酒づくりと並行し、若い世代にも受け入れられる新しい日本酒づくりに取り組むことが、これからの酒蔵のあるべき姿のようだ。他の酒蔵にはない石蔵を活用し、普段日本酒を飲まない方に来てもらえるような集客施設化に向けて取り組む必要性を痛感している。「今後は母屋、茶室、庭園を利活用し、エンターテーメントな空間にリニューアルし、家族で酒蔵見学できるような方向に持っていき、最後に試飲してもらい、日本酒ってこんなに美味しいのだと感激して買って帰ってもらえるようにしたい。」と東社長は思い描く。国登録有形文化財になっている石蔵の維持管理も重要な責務のため、今後は文化財の酒蔵を維持するために日本酒を一緒に楽しめる空間を構築していきたい考えだ。「文化財の維持は大変ですが、仕込みの終わった夏場は時間的余裕ができるため、文化遺産の維持にも従業員の手を借りて、新しい日本酒文化を築いていきたい。」と国登録文化財である石蔵の維持保存にも余念がない。

東 社長
会社概要
| 商号 | 東酒造株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 万延元年(1860年) |
| 代表者 | 代表取締役 東 祐輔 |
| 住所 | 小松市野田町丁35 |
| 電話 | 0761-22-2301 |
| URL | www.sake-sinsen.co.jp/ |