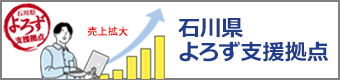本文
独自のストライプ裏地織物技術をベースに織機に改良を加え、受注ゾーン拡大につなげる 廣瀬機業場
廣瀬機業場
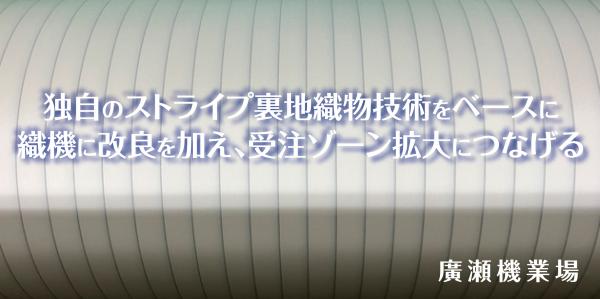
中能登町周辺の地域は、能登上布の里として知られる歴史ある繊維の産地。全盛時には一つの町内に何十軒もの機屋が軒を並べ、糸を織る機械の音が一帯に鳴り響いていたもの。今では数えられる程に機屋は激減し、七尾市伊久留地区では2軒を残すのみに。その1軒、廣瀬機業場は背広の裏地に使われるキュプラ織物では全国的なシェアを誇っている。同社3代目の廣瀬宜之さんにお話を伺った。
背広のストライプ裏地でトップシェア
中能登町をはじめ能登一帯は、戦後の復興期にあって繊維商社の下請け機屋として賃加工で生計を立て、繊維王国石川と称されるほど、石川の繊維産業は隆盛を極めていた。ところが、オイルショック、円高不況、バブル崩壊と、昭和から平成に時代が変わるのと時を同じくして、中国からの安価な縫製品が洪水のように入り込むようになり、地元の繊維商社が次々と破綻し、その下請けをしていた能登の機屋も仕事がなくなり、次々と廃業せざるを得なくなる。そんな厳しい環境下に晒されながらも、大手商社から背広の袖裏に使われるストライプ裏地を専業に下請けしていた同社は、百貨店やスーツの全国チェーンへの納品で、堅実に歩んできていた。ストライプの裏地を生産しているのは全国に同社を含めて3社しかないこともあり、現在は年間3万反(全盛期は9万反)を生産し、全国シェア1位で推移してきている。


コロナ禍で新たな仕事に挑戦
2020年からのコロナ禍で、在宅勤務、テレワークが推進され、スーツが売れなくなり、裏地のないセットアップが普及し始めるなど、逆風が吹き始める。コロナ禍になってほぼ仕事がなくなり、24台ある織機の3分の2が止まってしまい、近隣の機屋を廻って自社で受けられる下請け仕事を少しずつ回してもらう他社の仕事を含めて、何とか8台だけ稼働していたという。こうした経験したことのない状況を乗り切るためには、裏地以外の仕事を増やす必要性に迫られる。そこで、県の補助金を活用して織機に改良を加えることに。20年あまり使用してきている同社の織機は、一種類の横糸を通す構造だったことから、同時に2種類の横糸を通して織れるよう改良を加え、ストライプの裏地以外の生地を織れるようにしたことで、産業資材のインクリボン、包装資材のリボン、卒業アルバムの布表紙、着物の襦袢の襟生地など、新たな用途向けが徐々に増えてきている。


他社の仕事を開拓し、リスク分散に努める
コロナ禍で激減した稼働率も、こうした廣瀬さんの努力の甲斐あって、ほぼ機械がフル稼働するまでに回復してきている。従来からのストライプの裏地の量は減ったものの、それ以外の裏地の需要が回復してきたことから、受注量はほぼ元に戻りつつある状況のよう。とはいえ、総体的な量は減ってきているのは間違いないものの、廃業する機屋も全国的に見れば相当数あることから、そうしたところの仕事が同社にシフトしてきていることも仕事量が回復している要因の一つ。現在は、従来からの商社の仕事が全体の7割(うち約半分が裏地関係、残りは他用途向け)、残りの3割が他社からの新たな仕事で、「新しい仕事のウエイトを徐々に高めていき、1社だけの下請けだけではリスクが大きいため、複数社からの仕事を受けることで、景気の波で左右されるリスクを少しでも緩和できる方向へ持ってきたい。」と意欲的だ。


貴重な若手後継者として日々奮闘
10年あまり前から、石川県繊維協会が旗を振り、賃加工から脱却し、自ら作り自ら売る「自販」への転換を推進してきているが、現実問題として、目の前の仕事をこなすことで手一杯であるのも事実。なぜなら24時間稼働している織機が止まった時に、素早くその原因を除去し、再稼働させる作業も自らがやらなければならないため、夜中も定期的に工場へ織機の稼働状況を確認しに行くのが日課で、とても自社ブランドや自販に一歩踏み出す状況にはない。それでも、自社でできることは最大限自社でこなし、受ける仕事の幅を広げることで、リスク分散につなげるなど、機屋の中では数少ない若手後継者として日々奮闘している様子が見て取れる。


繊維事業者の有志で「テクシる」を結成
先人より受け継がれてきた伝統的なものづくりの精神を尊び、その価値観を共有し、後世に着実に継承していくことを目的に、中能登町と七尾市にある繊維事業者有志の7社(武部織物・清酒織物・高幸織物・岡崎織物・丸三織布・新日本テックス・廣瀬機業場)で結成された「テクシる」。歴史と由緒ある能登上布から派生し、ポリエステルやナイロンから天然繊維により近い質感を持つ合成繊維、和紙を利用した繊維、スポーツ等に特化した機能性繊維等々、化学合成繊維の分野では、高いレベルの技術力を有する繊維産地として世界的に知られている産地の事業者であることを誇りに、新しい時代に向けたものづくりに取り組んでいる。2023年11月1日・2日に東京ビッグサイトで開催されたジャパンクリエーションに「テクシる」チームとして、麻とポリエステルを使った新たな洗える生地を出展。まだ具体的な商品化までには至っていないものの、産地をアピールする「NEO能登上布」発信活動の一つと捉えている。中能登町の織物デザインセンターにある20万点のデザインサンプルも活用し、進化した能登上布の独創的な商品を是非発表してもらいたい。


設備更新と人材確保が今後の課題
正確な数は今となっては不明だが、昭和40年代までは、集落の中に十数軒の機屋があったようだが、現在では2軒を残すのみ。それだけ繊維を取り巻く環境が激変してきた証左である。県内の繊維産業を牽引する企業が主に取り組むスポーツ衣料で使用されるのはポリエステル繊維のため、同社の使っている織機に比べると織り幅が格段に広く、自前の織機は使えない。そうした分野に取り組むためには織機を新たに導入する必要があり、新しい織機を10台入れるとなると何千万円単位の設備投資となるため、二の足を踏まざるを得ない。とはいえ、現在使っている織機も20年を超えていることから、あと10年以内には更新の時期を迎える。「自分の年齢と事業の将来、借金を返済し終わる時点の年齢を考えると、そろそろ真剣に考えないといけないタイミングなのかもしれません。」と廣瀬さんは唇を噛みしめる。現在、工場を手伝ってくれている人たちの高齢化も進んでいることから、人材確保も含め乗り越えていかなければならない課題はあるものの、若さと情熱で課題を解決し、さらなる新たな一歩を踏み出してもらいたい。


廣瀬 宜之さん
会社概要
| 店名 | 廣瀬機業場 |
|---|---|
| 創業 | 1961年 |
| 代表者 | 廣瀬 明 |
| 住所 | 七尾市伊久留ロ部20番地 |
| 電話 | 0767-68-2364 |