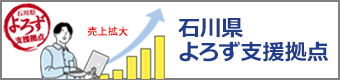本文
革新的な電子轆轤を自社開発し、山中漆器産地の新時代を支える! 乙綺木工
乙綺木工(いつきもっこう)

石川県を代表する伝統工芸の一つに山中漆器がある。バブル崩壊以降、県内の伝統的工芸品産地は厳しい環境下に晒され、山中漆器の産業従事者数も全盛期に比べ縮小してきている。そんな中にあって、山中漆器産地の将来に一筋の光明とも言うべき、革新的な電子轆轤機械を、県外から移住し、独立起業した若手職人・濱口徹さんが開発した。乙綺(いつき)木工代表の濱口徹さんにお話を伺った。
モノづくり好きが高じて木工職人に
大阪で生まれ育った濱口さんは、子どもの頃からモノづくりが好きで、大人になったら大工になりたいと思っていた。高校を卒業すると、京都伝統工芸大学校の木工芸専攻に進み、京指物に代表される伝統的な手づくり家具職人になるべく4年間腕を磨く。卒業後、同大学校の先輩が和歌山県で紀州桐箪笥を製造・販売する会社に入社する。6年あまりの勤務を経て、暖簾分けしてもらい独立する。独立はしたものの、1本あたり数十万円~数百万円する伝統家具の製造だけでは需要が減ってきており、現実問題として食べていくことは難しい。何かもう一つ違う木工の加工技術を身に付けなければ・・と考えていたところ、大学校時代のの同級生に山中漆器を製造販売している親友がおり、山中漆器産地が木地師の高齢化、後継者難に直面して困っていることを、以前から耳にしていた。そして山中漆器産地には、木工轆轤を使った挽物を学べる研修所があることを知る。28歳の時に山中漆器挽物轆轤技術研修所に入所し、挽物技術を身に付ける道を選択する。



山中漆器産地の製品 加工に使用する鉋
木地師に必須の機械、轆轤がない現状に危機感
山中漆器挽物轆轤技術研修所を卒業し、同所の独立支援工房で3年間就業している間に、山中漆器の木地を削るために必要な轆轤という機械が、現在は製造されておらず、独立する職人は、引退した職人が使っていた中古の轆轤を譲り受けて使うしかないという現状を知る。数年前まで山中産地を回って轆轤のメンテナンスをしていた職人が廃業したこともあり、轆轤の存続が危ぶまれる状態だった。山中式轆轤の修理や、復刻して新しく製造できる会社もなく、数十年前に製造され使い古され傷んだ轆轤しかない。新しく事業を始めるにしても、壊れた時に修理できる人がいないのでは、リスクが高すぎて中古を買うことは避けたい。山中式轆轤は、単純な機械に見えて実は複雑な構造のため、これだけ技術が発達した時代であっても轆轤のノウハウがないと、その通りに製造することは難しい。この状況では、技術は身に付けたものの轆轤がなくて、仕事をしたくても仕事ができない。それなら自分で新しい轆轤機械を造るしかないと思い立つ。


試作を重ねて完成した木工用轆轤
自らのモノづくりポリシーを社名に
濱口さんが独立支援工房を出るタイミングに、山代温泉で建具店を営んでいた工場が売りに出ていて、それまで使用していた木工関係の機械をそのまま譲り受けることもできたため、初期投資を抑えつつ活動拠点を構えることができた。次は社名をどうするか・・。「18歳から10年以上に渡って伝統技術の研鑽を続けてきて、私の手掛けた商品は仕上がりが綺麗なものをお客様に提供したい。」と力を込める。そんな思いから、社名には「綺」の字ともう一文字、意味のある文字を入れたいと考える。これまでものづくりを続けてきた中で、今の世の中にあるものは、美術館に並ぶ国宝のような、技術的に素晴らしいが手に入らないほど高額な「美術品」か、一般市場に出回っている大量生産の安価な「日用消耗品」かの二極化が激しく、その中間にあるはずの「高級品」(本当の意味での工芸品)が少ないと感じていた。これからの伝統産業の価値を再認識してもらう為には、鑑賞するだけの美術品を(甲)とするなら、少し背伸びすれば購入することができ、実際に使って良さを感じてもらえる高級品(乙)のラインの物を作っていくことが重要と考え、(乙)の部分にあたる商品を製造し、(綺麗)なものづくりで、木工品の付加価値を上げていきたいとの思いを込め「乙綺(いつき)木工」と命名する。


こけし製造用の轆轤に可能性を見い出す
そんなタイミングで、仙台でこけし製造に使われるこけし用の轆轤を造っている会社があることを、宮城県にいる研修所の卒業生から情報がもたらされた。山中漆器の轆轤は、四畳半の部屋が埋まるほど大きいのに対し、こけし用の轆轤は持ち運べるコンパクトなもので、それを見たベテラン職人からは「こんな小さな轆轤で仕事ができるのか」と懐疑的な声が上がる。それでも濱口さんにとっては、轆轤の有無がこれからの人生を左右するだけに、何とか改良を加えることで、山中漆器の木地を削ることに叶う轆轤に改造できないだろうかと微かな望みを抱く。こけし用轆轤の耐久試験を始めたところ、山中漆器の轆轤はペダルの踏み加減で、段階的にスピードコントロールができるのに対し、こけしの轆轤は回転スピードのコントロールができず、一定速度で正転、逆転するだけのものだった。これでは山中漆器の木地造りの作業ができないため、電子制御で作動する車のアクセルペダルのような機構が何かないか、ネットや知り合いなど、様々な手を使って探し始める。さらには、山中漆器挽物轆轤技術研修所から石川県工業試験場につないでもらい、スピードをコントロールする装置が作れないか相談に行き、技術的な開発に着手する。


1年がかりで理想のペダルにたどり着く
10年以上現場で作業してきた濱口さんは、工業用機械はかなり頑丈に造られた耐久度の高いものでないとすぐに壊れることを経験していた。当初、工業試験場からミシンのペダルで代用できるのではないかと提案されるも、プラスチックのペダルは試験を重ねることで壊れてしまった。ペダルの耐久度と踏み加減の読み取りにも高い精度が要求されるため、工業用のペダルを探すことに。ネットを駆使してあちこち探すも、購入できない車のペダルに行き当たるばかり。1年余り探し回って漸く行き着いたのが、ポテンシャルメーターを製造している会社で、一般市販はしていなかったが、同社のホームページに試作例としてフットペダル付きのものを見つける。そこから技術資料を取り込み、自分たちが造ろうとしているスピードコントロールペダルとして、電気的に使えるものなのかを工業試験場に確認してもらったところ、OKの返事を得られたことで試作機の製造が本格化する。石川県の補助金を活用し、令和5年1月から乙綺電子轆轤の商品名での販売を新事業としてスタート。試験導入も含めてこれまでに10程度が納品され、現場で使用されている。足掛け4年余りを要したものの、これで今後、研修所を卒業して新たに職人としてスタートする人たちに新品の電子轆轤の販売・設置・メンテナンスを行えるビジネスモデルが確立する。コロナ禍を経て原材料費や物流費の高騰もあり、販売価格は一台200万円(税別)~とのこと。


電子轆轤が作業効率をアップし、木地加工の可能性を広げる
既存の山中漆器の轆轤はスピード調整が数段階程度だったのに対し、電子制御で無段階に回転速度が調整できることから、ペダルの踏み加減で、車のアクセルペダルと同様に、回転速度を自在に調整でき、木地を削る作業効率が格段にアップできることが最大の特徴。さらに、削る木地をはめ込む部分が従来はひとつのサイズに限定されていたが、同社の電子轆轤では、木地を掴む部分をチャックに付け替えることで、あらゆるサイズの木地をチャックの開閉で掴める点も従来の轆轤にはない大きな魅力。そう遠くない将来、修理できる業者もなく、どんなに素晴らしい技術を持った職人が沢山いても、轆轤がなくなったら産地そのものが消滅してしまう危機的状況に陥っていたに違いない。そう考えると、乙綺木工の電子轆轤がこれからの山中漆器産地にとっての救世主であると同時に、これからの山中漆器産地にとって、なくてはならない頼もしい縁の下の力持ちに他ならない。山中漆器産地では、職人と製造卸業者が一丸となって、新ブランドを立ち上げ、23年9月にその第一弾として木製漆器の新ブランド「もののぐ」を発表。23年中には近代漆器の新ブランドも発表予定。こうした新しいうねりが新しい風を起こし、山中漆器がさらなる進化・変化を遂げることを期待したい。

会社概要
| 店名 | 乙綺木工(いつきもっこう) |
|---|---|
| 代表 | 濱口 徹 |
| 住所 | 加賀市山代温泉44-10-3 |
| 電話 | 090-6247-0231 |