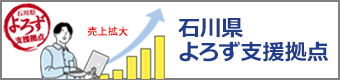本文
九谷産地の花坂陶石を原料に、自社開発の釉薬で焼成し、環境に優しいSDGsな商品展開で新時代を拓く (株)宮創製陶所
株式会社宮創製陶所

歴史を遡ると、再興九谷「若杉窯」が開窯してから200年以上にわたって伝承されてきた伝統工芸・九谷焼。バブル期までは栄華を誇っていた産地も、バブル崩壊、リーマンショック、コロナ禍の荒波に揉まれ、産地規模も窯元も従事者数も激減し、厳しい環境下に晒されている。そんな中、大正3年の創業から110年の長きにわたり、招き猫やフクロウの置物の素地専門に歩んできた宮創製陶所が、県の補助事業を活用し新たな時代が求めるSDGsなモノづくりに挑んでいる。同社五代目の宮本淑博代表取締役にお話を伺った。
素地製陶一筋に100有余年
宮創製陶所は、九谷焼の置物の素地製陶一筋に一世紀以上続いている老舗。九谷五彩に代表される華やかな絵付けが特徴の九谷焼の世界にあって、素地づくりは裏方的な仕事のため、一般的にはあまり知られていないが、同社は置物素地の世界において高度な技術力を有する屈指の製陶所である。その背景には、九谷焼の置物の隆盛期であった、大正・昭和時代の高度な技を持った職人たちの手によって作られた様々な型を多く所有しており、それが最大の強みであると同時に貴重な財産でもある。バブル崩壊、リーマンショック、コロナ禍と、伝統産業の業界は度重なる荒波に揉まれ、厳しい環境下に晒されていることは否めないものの、ピンチこそチャンスの発想で、保存されている多くの型を活用し、若手作家とのコラボレーション、九谷焼の新たな魅力の創出・再発見・発信に精力的に取り組んでいる。


花坂陶石の残土を再利用し、新たな釉薬を開発
バブル崩壊、リーマンショックを経て、九谷焼の置物の需要は、減少傾向が長く続いていたが、北陸新幹線の金沢開業を契機に、観光客が急増し、それに伴って九谷焼の置物が売れるように。ようやく長いトンネルを抜け、回復の兆しが見えてきていたところへコロナ禍が到来し、再び減少傾向に転ずる。そうした中、県の補助金を活用し、九谷焼業界初のSDGsに対応した8色のオリジナル釉薬による新商品の開発をスタートさせる。これは、花坂陶石から九谷焼の陶土(坏土)にする工程で、不純物として取り除かれた残土(従来は産業廃棄物として業者が回収)を、近年は、リサイル、リユース、SDGsが叫ばれる世の中になってきていることもあり、廃棄している残土を何とか有効活用できないかと、石川県立九谷焼技術研修所ならびに九谷焼技術センターに足を運び、釉薬について一から学び直すと同時に、この残土を金属鉱物と合わせて釉薬に混ぜる試作を繰り返す中から、これまでの九谷焼にはない、ざらざらとしたマットな質感に仕上がり、なおかつカラフルな色味に仕上がるオリジナルの釉薬開発に成功する。他産地の釉薬や素地を使い、それに絵付けや転写したものを九谷焼として販売することに疑問を感じていたこともあり、九谷の産地由来のものである花坂陶石を素地に使い、絵付け、転写、焼成したものだけが九谷焼であると、明確に胸を張って言えるモノづくりを標榜したいとの熱き思いが開発の原動力。


カラフルカラーの招き猫
オリジナル釉薬が開発できたことで、青・赤・黄・白・黒を中心に、淡い色味のパステル調や鮮やかなビビッド調など、様々なカラー展開が可能となる。置物の代表格は何といっても招き猫。右手を上げている招き猫は金運を招き、左手を上げている招き猫は人を招くとして古来より親しまれている。オリジナルの釉薬を使い、九谷焼には珍しいマットな質感とカラーにこだわった令和の時代の招き猫をシリーズ展開。職人が一つひとつ手作業で色付けするため、全てが微妙に異なり、釉薬による風合い、焼き物特有の個性が楽しめるのも魅力の商品。人のつながりでご縁ができた金沢市内にある「ギャラリーショップ歪/wai」で販売されているほか、東山のお土産店にも置かれている。商品の原型の試作から花坂陶石を使った素地づくり、釉薬での着色までを一貫して引き受けられることにより、企画から商品化まで効率よく進められ、九谷焼の置物にとどまることなく、雑貨やインテリアとの親和性の高い商品開発が可能となり、異業種とのコラボレーションも進められている。


サイズ 高さ6cm 価格 2、750円(税込)
九谷焼Plantpot「Condo」 、hamaの商品化
人間の暮らし、生活空間において、心に安らぎを与えてくれるものの一つに植物がある。植物は本来大地に根付いて育つのが自然の姿であるが、それを人間のエゴで鉢植えにし、狭い空間に閉じ込めている。それならせめて自然由来に近い住み良さを感じてもらいたいと、「Condo」を制作。大地から生まれた素材を使って作り、ネーミングのCondoは、植物にとって大切な根(こん)と土(ど)に由来する。また、九谷焼の火入れの際に製品の歪みを防ぐ目的で素焼きの下に敷かれる「ハマ」。これまで焼き上がりと同時に破棄されていた「ハマ」に新たな用途を持たせることを閃く。ハマは石膏製で吸水性がよく、真っ白な見た目は清潔感もある。廃棄されるハマを使い手のアイデアで日常を豊かにするパーツとして役立ててもらおうとの思いから「kutani-reuse/hama」として商品化。


インテリアの分野にも可能性が・・
磁器を削る際に発生する削り屑も従来は廃棄されていたが、それをさらに細かく粉砕し、アマニ油で溶いて木材に塗ってみると、これまでにない風合いに仕上がる新たな塗料に生まれ変わった。しかも九谷由来の素材であるため環境にもよく、SDGsにも叶う塗料としてインテリアの用途につながる。壁や棚、床材に塗るワークショップが金沢のデザイン事務所で行われ、県外の特殊塗装会社の専門家を招聘して開催したところ、塗料が参加者から好評を得たという。実際に塗ってみると、九谷の粒子は非常に細かいため、とても滑らかな塗料に仕上がり、素人でも塗りやすいとのこと。「何事も基本的に捨てたくないというのが、私のテーマであり、常に何か新たな用途が見つけられないか、日々試行錯誤するのが楽しみです。」と宮本さんは顔を綻ばす。この塗料は光沢感のある仕上がりになり、プラスチックでコーティングしたかのような風合いに塗りあがることも分かった。


九谷産地に新風を吹き込み、さらなる100年を見据える
「環境に優しい商品はいろいろ世の中にあるものの、ただ商品棚に並んでいるのを見ただけでは理解してもらえない。作り手がどんな思いで作り、環境にどのように配慮しているこだわりの商品なのか、そのストーリーを語ることで、買い手のハートにスイッチが入り、それならと目の色が変わる瞬間があるのです。」と宮本さんは目を輝かせる。そんな同社のSDGsな取り組みに賛同したのが、小松市出身の書道家でユーチューバーの石野華鳳さん。共同で商品化した「墨池」はヒット商品に。従来品にないオリジナル釉薬によるマットな色味の仕上がりが好評で、月に20~30個ペースで売れている。石野さんには3万人あまりのフォロワーがおり、SNSを見たファンが主な購入層とのこと。いろんな人とのつながりの中から、循環型のビジネス展開を実践している宮本さんの経営姿勢に共感するSDGs思考の人的ネットワークが次々と広がりを見せ、同社の目指す循環型ビジネスが文字通り好循環し始めている。高齢化、後継者難で職人も窯元も減少傾向にある中で、産地内で数少ない若手である宮本さんは、何一つ捨てるところなく、全て商品につながる好循環型ビジネスを確立し、常に一歩先を目指して九谷産地に新たな風を起こすべく邁進中。次代を担う子息にバトンを渡した時に、悠々自適であれるよう、さらなる100年につながる盤石な経営基盤の確立に余念がない。

墨 池

宮本 淑博 氏
会社概要
| 店名 | 株式会社宮創製陶所 |
|---|---|
| 創業 | 大正3年 |
| 住所 | 小松市八幡乙82 |
| 代表 | 代表取締役 宮本 淑博 |
| 電話 | 0761-47-0026 |
| URL | https://www.miyasou2020.com |