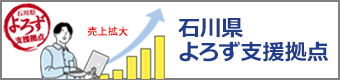本文
安全第一、社員の健康第一を徹底し、キラリと光る先進的なバス会社を標榜! (株)丸一観光
↵
株式会社 丸一観光

「赤い花 青い空 みどりはすすむ すすむ みどりのバス みどりのバス 丸一観光」のフレーズは、思わず口ずさむ人も多いのではないだろうか。七尾市に本社を構えるバス会社・株式会社丸一観光のテレビCMソングである。地元の人たちに少しでも親しみを感じてもらえるよう同社の木下徳泰社長がされた。昭和49年に運送業として創業してから51年目を迎える同社の木下恒喜専務取締役に、同社の先進的な取組や今後の展望についてお話をうかがった。
七尾の地で創業から51年
1965年に初代木下彬氏が運送業を創業したのが同社の原点。運送業を始めた当初から、ゆくゆくは観光バス事業にも進出したいとの思いを温め続けていた初代は、運送業が軌道に乗り始めた頃から、一般貸切旅客運送業の免許を取得すべく、足しげく名古屋の中部運輸局に通い、自社の業務実績や自社の安全管理に対する取り組み等をアピールし続け、その努力が結実し、1983年に一般貸切旅客運送業の認可が下り、念願だったバス運送事業を開始する。2011年に貸切バス事業者安全評価認定制度一つ星認定を受けて以来、二つ星、三つ星とステップアップし、2023年まで12年間連続で三つ星認定を達成。同年には、働きやすい職場認証制度星二つ、2025年には健康経営優良法人2025中小規模法人部門に認定される。こうした実績を積み重ねてきて、現在は大型バス30台、中型バス5台、小型バス10台、高速乗り合いバス4台の規模に成長している。



安全は同社の一丁目一番地
(運転士の健康維持管理の徹底)
近年の運転士の高年齢化もあって、健康起因による事故が増加傾向にあることから、同社では日頃から運転士の健康管理には特に力を注いでいる。年1回の健康診断を会社負担で実施し、要精密検査・要治療と判断された場合は、早急にかかりつけ医を受診させ、医師の見解を基に乗務の可否を判断。また、睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策として、年1回の簡易検査を会社負担で実施し、要精密検査判定を受けた場合は、1泊2日の終夜睡眠ポリグラフ検査を会社補助で実施し、検査時間は労働時間扱いとしている。ポリグラフ検査で要治療と判断された場合は、乗務を停止して治療を開始し、運転業務が再開できる程度の治療効果を医師から認められ、証明を受けたのちに復帰させている。頭部MRI検査及び胸部CT検査を3年に1回会社負担で実施し、異常所見があるものに対しては、精密検査を実施。再受診や精密検査は労働時間内とし費用補助している。
(運転時における事故リスク低減対策)
乗務前の血圧測定、アルコールチェック、注意喚起を日々徹底することはもちろんのこと、運転士にはスマートウォッチ型のAI運行管理ツールを貸与し、AIがリアルタイムの心拍データを分析し、本人が自覚する以前の危険な兆候を検知している。同時にドライブレコーダーのカメラで、リアルタイムに運転士の目の動きや、居眠り運転の兆候がないかを管理。スマートウォッチを振動させて覚醒させる遠隔操作も可能とのこと。そのほか、管理栄養士による定期的な健康面談の実施やインフルエンザ予防接種を会社負担で行っている。
(運転士に対する教育体制)
最新AIドライブレコーダーと全方向6カメラを接続したデジタルタコグラフとドライブレコーダーの2つのシステムで、リアルタイムで運転士の顔の状況を把握し、目線やからだの動きをAIが分析し、瞬時に必要な指導を無線にて行っている。運行後には、運転士一人一人にデータ化された各人の運転行動を可視化し、「振り返る」機会を設け、同社の約50名の運転士に気づきを与えることで、事故の未然防止と安全に対する意識づけを習慣化している。
(車両安全性能)
同社では、事故を限りなくゼロに近づけるため、最先端の各種装置を備えた車両を配備している。衝突被害軽減ブレーキ、レーンキーピングアシスト、車線逸脱防止支援装置、車線内維持支援機能、車線逸脱警報、車両安定制御システム、電子制御ブレーキシステム、ドライバー異常時対応システム等々。
「こうしたドライバーの健康管理に対する徹底した安全安心への取り組みは、全国的に見ても、当社の規模でここまでやっている会社はないと、取引先の旅行会社から高く評価されています。」と木下専務は胸を張る。
運転士の確保が喫緊の課題
ご多聞に漏れず、同社においても運転士の確保が喫緊の課題。現状では平均年齢が50代前半とのことで、この先10年程度の間に、いかにして若手の運転士を確保し、育てるかが会社の将来を左右すると言っても過言ではない。法令順守が絶対条件のため、あらゆる項目をデータベース化し、デジタルで徹底した管理をしているものの、バスが車庫から出発した先は運転士に託される。一回の乗務を終えて帰社してから次の乗務まで、最低でも9時間以上の休養を取ることが法令で定められている。その点は厳格に順守している。やり甲斐の面では、毎年給料のベースアップを実施しているとのこと。同社は東京までの高速乗り合いバスを運行しているが、かつては運転士二人体制で、途中で交代していたが、人手の確保が難しくなってきたことや長時間拘束が敬遠されることから、長野県内のバス会社と業務提携し、互いに運転士は一人で、長野で交代する形に変更し、運転士にとって距離も時間も身体への負担も軽減され、ウィンウィンの環境を構築している。


コロナ禍、能登半島地震の影響
バス業界にとって、人が移動しない世の中は商売が成り立たない。そんな空前絶後の状況が5年あまり続いた。この間、同社は国や県の助成金を活用し、限られたバス運行を続けながら、何とか事業を継続させてきた。「運転士の人たちは、運転が仕事のため、運転できない世の中になり、何人も離職していったのが残念でなりません。辞めた人は戻ってこないので・・。」と木下専務は唇を噛む。コロナ禍が明けた矢先に、能登半島地震、奥能登豪雨と大災害が続いたが、幸いにして同社は建物にも社員にも被害はなく、すぐに稼働できたという。七尾市の中でも和倉温泉が壊滅的な被害を受けたため、観光拠点がなくなった状況になり、能登の観光においては大きく落ち込んでいる。幸いにして、同社は、金沢駅や小松空港に到着した、県外から、海外からの旅行者を県内の観光地に運ぶ、外部からの需要が順調に推移していることから、事業全体を見渡すと、それほど大きな落ち込みはない。


新たに飲食部門に進出
七尾市内には昔からの小さな喫茶店はあるものの、広い駐車場を備え、多くの人が集まれる全国チェーンの店舗がなかったことから、お客様が幸せな時間を過ごせる空間づくりがしたいと思っていたタイミングで、縁あってコメダ珈琲のフランチャイズに入ることができた。とはいえFC事業だけに、1店舗だけでは成り立たないことから、七尾に続いてかほく市に2号店を出店したところで、近いうちに金沢市内でも新規事業を予定している。バス事業とは異なるものの、やはり人の問題は同じ悩みのようで、働く人を探すのに一番苦労しており、飲食事業では外国人も採用している。運送業においてもトラックやタクシーでは外国人ドライバーが出始めているものの、貸し切りバスの場合は、その都度行き先が異なり、路線バスのように何時何分にどこのバス停に止まるという決まったコースではないため、外国人運転士の誕生はあまり現実的ではないようだ。
若い人に自社に興味を持ってもらうために
お客さんはもちろん、求職者も、まずは丸一観光がどんな会社なのか、真っ先に見るのがホームページである。そのため、同社はホームページでの情報発信に力を入れており、細部にわたるまで作り込まれた出来上がり。さらに若い人材を確保するため、ショート動画を作成し、SNSで情報発信を始めたところで、まだまだ結果には繋がっていないものの、来春に一名ではあるが、若手運転士の採用が決まったとのこと。若い人たちは、土日は休みたいのに対し、観光バスは逆に土日が稼ぎ時と真逆の状況で、これが若手人材を確保する際の大きな障壁になっている。
まるいい取り組みに邁進中!
丸一観光とかかわる時間が、お客様にとって文字通りいい時間であって欲しいとの思いが「まるいい時間」というキャッチフレーズに込められている。と同時に、全社を挙げて「まるいいプロジェクト」と銘打ち、SDGsの実現に向けて日々小さな努力を積み重ねていくことで、ゆくゆくは目標に到達できるとの思いでもある。地元の和倉温泉の完全復活には、まだ数年は要すると思われるが、現時点でも県内全域の観光需要に対し、観光バスの供給は追いついていない状況。いかにして人を増やしていくか、運転士に選んでもらえる会社にしていくかが目下の課題である。若い世代から見て魅力ある会社としての地位を確立していくことと、同社の一丁目一番地である安全第一を同時並行で推進していかなければならない。「能登半島地震で能登地域の人口減少が加速していますが、地域から働く場所がなくなると、さらに加速してしまうため、丸一観光で働きたいと言ってもらえる会社にすることが目標であり、今後の時代の変化の中で切磋琢磨し、さらに規模を拡大することも視野に、地震を経験したことで能登の企業として頑張っていかなければとより強く思っています。」と決意を新たにする木下専務である。


本社外観 木下恒喜 専務
会社概要
| 商 号 | 株式会社 丸一観光 |
|---|---|
| 代 表 | 代表取締役 木下 徳泰 |
| 住 所 | 七尾市矢田町2-1 |
| 電 話 | 0767-53-6161 |
| U R L | www.maruichi-gp.co.jp |